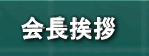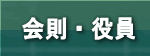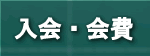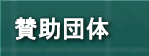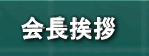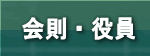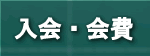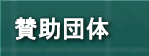平成18年7月9日(日)午後1時より、学校法人佐藤栄学園OLSビル2階 佐藤栄太郎記念講堂にて第3回摂食・嚥下研究会講演会が開催した。
講師には、埼玉県言語聴覚士会長白坂康俊氏、埼玉県作業療法士会理事中澤昌子氏、東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科講師千葉由美氏をお迎えし、約170名が参加した。
演題1:摂食・嚥下障害のリハビリテーション
 言語聴覚士からのアプローチ 言語聴覚士からのアプローチ
▽
講師 埼玉県言語聴覚士会長 白坂 康俊
1977年パリ大学第三学部を卒業、その後同大修士課程を修め、1981年国立身体障害者リハビリテーションセンター学院聴能言語専門職養成課程を卒業。同年、国立身体障害者リハビリテーションセンター第二機能回復訓練部入職。現在、同部言語聴覚士長。
本日は、ST(言語聴覚士)に向けてのスキル的な話しではなく、多職種の参加を踏まえて、臨床の立場から二点について話す。摂食・嚥下障害者の機能訓練では、我々の技術を向上させる事は当然のことながら、今我々が持っている基本的なスキルをきちんと使えば適切なリハが行なわれる。しかし、食べることから生じる日々の問題点に対して、機能訓練だけでは限界がある。その時に、行政を含めた社会が、この問題をどのように考えていくのか、ということである。
1.【
食べることの意味と役割
】
あまりに日常的であるが、実は、幅広い目的と役割りがある。肉体的側面では、バランスのよい栄養、成長、体格、体型の維持、エネルギーや水分補給、日常生活、仕事、スポーツなどの活動であり、精神的側面では、おいしいものを食べる喜び、ストレス解消、コミュニケーションの機会(一家団欒、デート、パーティー、仕事の打ち合わせ、あらゆる場面で人は食べる)である。食事中の発話数は、言語障害の有る無いにかかわらず極端に多い。食べる場面に参加できないのは大きな問題である。
2.【
摂食・嚥下障害リハの目標
】
目標としては、経口で栄養をとって欲しい。そして、味や雰囲気を楽しんでおいしく食べて、楽しく食事をしていただくことである。 軽度の障害の場合は、食べ方、食器、調理、姿勢などの工夫で、多少の制限、制約はあるが、健康な時とほぼ同じ食事ができる。中等度の障害の場合は、経口摂取を基本とするが、食物の形態、食べ方がかなり制限される。重度の障害の場合は、安全性を最優先させるために、生命の危険回避を優先して、経口摂取を断念せざるを得ない。しかし、食事の内容、調理法、姿勢、食べ方、食器などの制限や工夫で、少量を楽しみのために考えることはできる。
患者も家族と一緒に楽しく食事をしてほしい。また、食事を伴う家族旅行や、外食や旅行、知人・友人との食事を伴うお付き合いを大切にしてほしい。
3.【 まとめ 】
機能訓練には限界がある。体の障害に関しては、バリアフリーという概念が大変普及してきていて、ユニバーサルデザインという形に発展している。嚥下機能の制限に、食のバリアフリーという概念があってもいいのではないかと考えている。そのためには食物形態(味)のバリアフリー、すなわち栄養士、調理師までもまきこんだチームアプローチと、食べ方、場所、食べる時間のバリアフリーである。外出や旅行が楽しめるように、食のバリアフリーを実現したい。
摂食・嚥下障害はQOLの低下をきたす。そのためには、専門家の援助や、家族、および周囲の方々の理解と協力、また、社会の理解と協力が必要である。障害を持つ方に変化を求めるだけではいけない。社会の側が変化し対応する努力が必要である。埼玉県摂食嚥下研究会が、将来そのような役割りの一助をなすことを期待する。摂食・嚥下障害者には、必ず機能訓練を行い、機能制限にたいするアプローチから生ずる活動参加レベルの制限に、もっとしっかり目を向けるべきである。改善に限界があっても、社会の側からもっとできることがあるのではないかと考えている。
演題2:摂食・嚥下障害を呈した症例に対する顔面・頸部・胸郭のリラクセーション効果
 作業療法士 からのアプローチ 作業療法士 からのアプローチ
▽ 講師 埼玉県作業療法士会理事 中澤 昌子
1977年パリ大学第三学部を卒業、その後同大修士課程を修め、1981年国立身体障害者リハビリテーションセンター学院昭和52年東京都立府中リハビリテーション学院卒業。同年神奈川県総合リハビリテーションセンター就職。平成8年放送大学卒業。平成9年大宮共立病院就職。平成12年早稲田医療技術専門学校非常勤講師。平成18年小張総合病院就職。平成10年から現在まで埼玉県作業療法士会理事(財務担当) 。
1.【 口から食べる】
「口から食べる」という事は栄養補給し生命維持するために必要である。しかし、それだけでなく、交流・楽しみ・喜びなど生活の質に関わる事柄でもある。通常、作業療法士は片麻痺の上肢機能訓練・日常生活動作訓練、自助具の工夫、座位バランス・耐久性の向上などを通して、摂食・嚥下障害患者に対して間接的訓練を実施する事が多い。
発声・構音障害や嚥下障害、四肢・体幹に随意運動障害があり、痙性による頸部周囲の筋緊張が高い患者に、頸部周囲のマッサージ・全身のリラクセーションを行う。また、起居動作訓練・筋力強化訓練を行うことにより、頸筋や腹筋、背筋が強化され、胸郭のスムースな動きを引き出し、姿勢を改善することで、嚥下障害の改善を図ることができる。
今回示した症例は、入院当初、胃瘻を増設し、経口による楽しみとして昼食のみミキサー食を介助にて摂取していた。食事時間は1時間余り要していたが、4ヵ月後には40分程度で摂取できるようになった。7ヶ月後の現在では咳嗽・喀痰が可能になった。
認知機能では、高次脳障害や認知症に対して、半側空間無視には空間認知訓練。観念失行には、道具を限定して、反復訓練。注意障害には、カーテンなどで刺激を遮断して訓練をおこなう。上肢機能では、リーチ・把持・筋力・感覚機能を評価して、関節可動域訓練、手指機能訓練、筋トレ、模擬的食事などを使った動作訓練、自助具の工夫などをおこなう。姿勢機能では、頚部機能、体幹機能を評価して、頚部体幹リラクセーション、ストレッチ、筋トレ、ポジショニング、車いすなどの工夫などをおこなう。咀嚼・嚥下機能、呼吸機能では、口腔筋、嚥下筋、呼吸筋の評価をおこない、顔面・胸郭リラクセーション、マッサージ、側頭筋や咬筋や舌骨上筋群や舌骨下筋群や肋間筋や横隔膜の筋トレ、呼吸訓練、咳嗽訓練などをおこなう。
症例紹介 : M氏 女性 71歳 平成17年夏に、くも膜下出血。それ以前に脳梗塞で右片麻痺。四肢の体幹機能障害で以前から糖尿病を併発している。
平成17年11月当院入院時評価
意識清明なるも反応弱く、発声は見られない。随意性は、頚部、四肢、体幹殆んど動き無く、わずかに両膝を立てられるのみであった。筋緊張は、外姿勢でも体幹や左肩関節の伸展強く、緊張高く、背中が反っている状態であった。左上肢は、体幹より後方にあり突っ張っており、右上肢は、麻痺にて動かない。頚部の動きも全く無く、ベッドに縛り付けられた状態であった。関節可動域は制限が多々あり、ADLは全介助であった。
作業療法(OT)訓練内容
目的は、随意的に頚部・左上肢など動かせるようにし、嚥下能力やADL能力を向上させ、介助量を軽減させることとした。
昼食前に、看護師、介護士、家族へ指導し、顔面・頚部にたいしては、蒸しタオル・マッサージをおこない、頚部・体幹・上肢にたいしては、温熱・マッサージ・ストレッチ・体幹捻転・屈曲を他動的に仰臥位や側臥位でおこなった。坐位バランスや寝返りも導入している。効果としては、筋緊張減少により、食事時間の短縮や喀痰・咳嗽・顔を掻くなどの左上肢の使用が可能となった。
演題3:看護師からのアプローチ
▽ 講師 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 千葉 由美
1.【 予防の観点 】
平成18年4月の介護保険制度の改訂で、介護予防事業に係る市町村介護保険事業計画を推進するにあたり「介護予防に関する各研究班マニュアルについて」が示された。
改訂の主な骨子は、介護予防のために生活機能評価を総合的に行い、疾病の予防や治療の管理だけでなく、加齢に伴い出現する「廃用症候群」(生活不活発病)や「老年症候群」といったさまざまな日常生活における障害や危険な老化のサインを早期に発見し、早期に対応することであることが示されている。「生活機能評価」は65歳以上の高齢者のみならず、40歳以上の基本健康診査における生活機能評価に関する項目の理学的検査に、視診(口腔内を含む)、反復唾液嚥下テスト(RSST: Repetitve saliva swallowing test)が含まれてきた。通常、診察における摂食・嚥下障害における理学的検査のポイントとしては、十分とはいえないが、このような保健業務が含まれてきたことは非常に興味深い。
2.【 実践の観点 】
上記の他にも介護保険制度関連では、介護保険3施設共通のサービスで経口移行加算を見直して新設した「経口維持加算」が明記された。算定基準には、(1)医師による摂食・嚥下機能の適切な評価、(2)誤嚥が発生した場合の管理体制整備、(3)誤嚥防止のための食形態などの配慮、(4)(1)~(3)について医師や管理栄養士、看護職員、ケアマネジャーその他の職種が共同実施する体制の整備、が明示された。摂食・嚥下障害への評価法については、複数存在している。誤嚥の評価と予防法探索のために、特に臨床的に有効なのはVF(videofluorography)やVE(videoendoscopy)といった機能評価となる。しかし、医師らの中でも実現可能性の点から疑問視される声があがっていた。また、技術面では、摂食・嚥下障害を有する方への有効な基準化テストや用いる指標がいくつかあるが、いずれも実践的な部分での使用ができるよう身につけておく必要がある。また「摂食・嚥下5期」のそれぞれ評価すべきポイントがあり、用いる指標もそれぞれに存在している。各期への評価に基づく適切な介入が重要であり、対象の状況によっては、食形態のみならず、適切な体位選択を行うことの科学的根拠(エビデンス)はある程度得られている。さらに経口摂取ができないような重篤な状況におられる方に対してもアプローチする必要性があり、特に看護職の能力が問われる場面も今後、増えてくると思われる。
3.【 看護師の人材と職務 】
今回の診療報酬改定において「入院基本料の算定で月平均夜勤72時間以内などの新たな要件が通則として入り、看護師比率が厳しくなった。一方、疾患別リハビリテーション料のうち、従来の総合リハビリテーション施設Aに相当する基準が適用されることになった「脳血管疾患等リハビリテーション料(1)」の人員基準の見直しがあった。リハビリテーション関係の専門職において、常勤の理学療法士5人以上、作業療法士3人以上、言語聴覚士1人以上となっており、看護師のみならず、医療従事者(コ・メディカルスタッフ)の人材不足が共通の課題となっている。そのような中、広い範囲で活動拠点を有する看護職は、自ら摂食・嚥下障害を有する方のスクリーニング、評価を実施し、問題点を発見したら、具体的なケアプラン作成のために、多職種と円滑に連絡・調整をはかりながら、できる限り迅速に業務を具体化していくことが重要となる。また、これらのケアプラン作成のために必要な情報の交換は、多職種間の双方向で継続して行えるよう、予めお互いのキャリアや実現可能性の高い業務内容を整理しておき、看護師自らも摂食・嚥下障害への知識・技術に関する学習を深めることが必要である。
4.【 ケアシステムの構築 】
円滑なチーム医療の推進のためには、看護師の職務を含めた各職種の業務や役割分担が明確になるよう、病院や特定の活動範囲ごとに簡易版の業務マトリックスや地域連携のためのpathway(パスウェイ)などを作成したり、実際に用いる指標の選定や共通言語の定義化をしたり、あるいは書式や具体的内容を設定しておく必要がある。
嚥下訓練(経口摂取)の開始基準
①日中意識が覚醒していて、開口などの指示に従えること(失語症がある場合は掲示的な客観的判断が必要)
②全身状態が安定していること(呼吸状態が安定、痰が多くない、発熱がない、血圧が安定)
③医師の症状判断(脳病変の進行がない)
⑤改定水のみテストで嚥下反射を認める
⑥十分な咳(随意性又は反射性)ができる
⑦著しい舌運動、喉頭運動の低下がない
⑧口腔内が清潔で湿潤している
【病院:症例1】
●80歳代後半、両腸骨動脈瘤、陳旧性心筋梗塞
●目的:経口移行の可否判定(重症例)
●既往歴・経過:20年以上前より高血圧にて服薬加療中。喫煙歴が長く80歳になって間質性肺炎発症し、加療治癒。主疾患に対する治療目的で手術を施行した。全身麻酔手術後、抜管し、血圧低下(心臓機能低下)により、再挿管をし、以後挿抜管、肺炎を繰り返し、気管切開となる。約1ヵ月して経口開始に伴い、嚥下がうまくいかないことで、嚥下訓練を実施するが誤嚥を繰り返していた。しかし、その後誤嚥性肺炎を生じ、増悪と寛解を繰り返す。長期臥位のためじょく瘡を発生し、栄養管理は、経鼻管からの投与により転院。
●検査・評価:全身所見、摂食・嚥下機能の観察、水のみテスト、VE
●看護師介入
①診療補助:バイタルサインズ(脈拍、呼吸、血圧、体温)管理、投薬、身体的観察・モニタリング(症状、ビーパップ、肺、心臓、腎臓)、など
②療養上の世話:口腔ケア・清拭、じょく瘡ケア、体位交換・姿勢、吸引、嚥下訓練、感染管理など
【病院・症例2】
●70歳代半ば、閉塞性動脈硬化症
●目的:経口移行の可否判定(重症例)
●既往歴・経過:高血圧、2型糖尿病の既往あり。糖尿病のコントロール悪く、治療を実施後、全身麻酔手術後、糖尿病性腎障害もあり腎不全に伴う呼吸不全を生じ、気管切開術を施行し、人工呼吸器管理となる。急性心筋梗塞を併発し、薬物治療で軽快。人工呼吸器離脱し、腎機能も改善し、バイタルサインズも良好であった。覚醒状態は比較的よく、目での合図が可能な程度であった。しかし、ベッドサイドにて摂食・嚥下機能評価を試み、体位変換、唾液吸引、1回のVEでもバイタルサインズの変動が著しく、積極的な介入は口腔ケアに留まる。回復を待つが3ヶ月経過し、全身状態の増悪が顕著となった。
●検査・評価:全身所見、摂食・嚥下機能の観察、VE
●看護介入:
①診療補助:バイタルサインズ(血圧、脈拍、呼吸、体温)管理、投薬、身体的観察・モニタリング(症状、レスピレーター、肺、心臓、腎臓、内分泌)など
②療養上の世話:口腔ケア・清拭・フットケア、体位交換・姿勢、吸引、感染管理など
【病院・症例3】
●90歳前半、肺炎後廃用性症候群、両変形性膝関節症、誤嚥性肺炎
●目的:誤嚥の可否と代償法の判定(経口摂取例)
●既往歴・経過:2年前の秋、自宅で転倒、微熱、食欲低下を認め、都内某特定機能病院に入院となり、誤嚥性肺炎ほか診断される。軽快後、慢性期のリハビリ、加療目的で他病院へ転院。嚥下障害があり、誤嚥性肺炎を過去に複数回繰り返していた。リハビリは入院後、両変形性関節症のため痛み増強し、積極的介入はせず温存となる。いわゆる啜り食べなどもみられ入院中も熱発が時折、見られていたことからVF施行し、通常姿勢で誤嚥認められたがリクライニング60°、トロミ食で、誤嚥消失することが確認された。検査結果を踏まえた病棟プランニングを作成し、食前嚥下訓練(嚥下体操)を施行した。時折、むせがみられることから、異常身体所見のモニタリングも行った。以後、熱発の発生は消失した。1年程度すると認知症の悪化(中程度)、ADLの低下とともに肺炎罹患が見られるようになった。そこで、積極的嚥下訓練を実施したところ、嚥下機能の回復傾向がみられ、発熱が消失した。
●検査・評価:全身所見(問診含)、摂食・嚥下機能の観察、食事の取り方・内容、フードテスト、VF
●看護介入
①診療補助:バイタルサインズ(血圧、脈拍、呼吸、体温)管理、身体的観察・モニタリング(症状、肺など)
②療養上の世話:離床、口腔ケア・清拭、体位・姿勢(リクライニング60°、頭部前屈など)、食事形態、嚥下訓練、コミュニケーションなど
5.【 看護職に求められる課題 】 看護職が対象とする摂食・嚥下障害を有する方のライフステージは、新生児からはじまり高齢者までとその幅は広い。また、疾患や病期によって、摂食・嚥下障害の症状の現れ方が異なってくることがあるので、ライフステージに応じた解剖、生理学などの必要な医学、歯科学的な知識の理解とともに、全身状況を系統的に評価できるようフィジカルアセスメントなどの基本的技術の十分な習得が必要と考える。 |